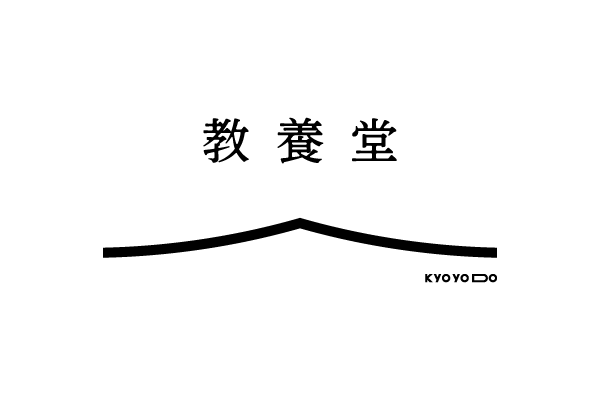勉強の話 2018年4月12日|木曜日
原作者が解けない入試問題
あらためて、原作者が解けない入試問題とは。
編集工学を提唱する著述家の松岡正剛氏の書評サイト「千夜千冊」(1670夜)に国語の入試問題に関しての興味深い内容が取り上げられていました。
『国語入試問題必勝法』(講談社文庫 清水義則 著)
『国語入試問題必勝法』は入試問題を風刺したパロディーの名著です。
そして入試問題に対するシニカルな批評でもあります。
以下が、松岡正剛氏の書評の最後にある興味深い内容です。
『ところで、私事ながら大事なことを付け加えておきたい。わが国語試験能力にかかわることだ。
実はぼくの文章はこれまで大学入試から中学の国語問題まで、何度も使われてきた。数えてはいないが、50回は越えていると思う。たとえば『日本という方法』が広島大学・佛教大学・岐阜大学、日比谷高校などに、『知の編集工学』が神戸芸工大・愛知淑徳大学・久留米大・三重大学などに、『日本数寄』が京都精華大・千葉商科大・広島国際大などに、千夜千冊あれこれが立命館大・関西学院大・桃山学院大などに使われた。
意外だったのは『フラジャイル』を防衛大学校が問題文にしたことだ。『試験によく出る松岡正剛』という本になるねえと、スタッフたちに冗談を言ったほどだ。
試験問題だから使用前は知らされない。使用後に事務的なペーパーが郵送されてきて、「貴殿の『花鳥風月の科学』の✕✕✕✕の個所を****の試験問題に使用しました」と連絡がくる。なかには問題文とともに送られるので、試しに解いてみるのだが、これがなんとほとんどハズれてしまうのだ。とくに「傍線の箇所と同じ意味をあらわしているのは、イロハニホのどれか」という問題が、からっきしできない。みんな当たっているように思うのだ。
おそらくその文脈でその文章を書いた本人は、さまざまな含意をもってその個所を書いているので、イロハニホのいずれもカバーしてしまうからなのだろう。そうだとすると月坂先生が正しいのかもしれない。まっこと、国語入試問題とは奇っ怪なものである。』
古くから都市伝説のように語られてきた「国語入試問題」問題。
つまり、当の原作者も解けない国語入試というものです。
笑い話の一つだろうと思っていましたが、最近になって書かれたこの書評を読むと愕然とします。
松岡正剛氏はおそらく日本で一、二を争うほどの読書量と読解力をお持ちの博覧強記の思想家です。
その人の口から「これがほとんどハズれてしまうのだ」というから、悪い冗談です。
日本のこれまでの営々と築きあげてきた入試問題の作成技術に欠陥はないのか、という懸念が生じます。
あまり良い冗談ではないなということと、ある種のニヒリズムを感じてしまいます。
逆に国語の入試問題に苦しめられたほとんど大多数の大人にとっては、胸のつっかえが取れる話でもありますが。
試験問題だから使用前は原作者にも知らされない
というのもいわゆるエアーポケットかと思います。
原作者ですら守秘義務のしばりで、後から「こういう問題でした。」という事後承諾なのです。
例えばある原作本からの映画化やドラマ化となれば、原作者から手が離れ、プロデューサーや監督、演出家の影響下に入ります。
往々にして原作と違った作品になることもあります。
原作を超える完成度の高い作品になることもありますし、その逆もあります。
しかし入試問題となると、あまりに原作者の意図と出題意図がちがうのはどうかと思います。やはり原作者に対しての敬意は要ると思います。
塾講師としては仕方がないのですが、もちろん出題者の意図にかなう解答方法を教えます。
むしろ入試問題であれば「勝手な解釈」は許されず、いかに出題のねらいを論理的に考察していくかが問われるのです。
そうなると直感で頼るのではなく、極めて理論的に吟味していかなければ正解に至りません。
たとえば「消去法」はその最たるものです。
原作者<出題者
あえて出題者側の観点に立つと、「あなたが志望するわが校の入試問題については、わが校が責任をもって作っておるから、わが校の内在的論理を把握してわが校の門をたたいてほしい。文句があるなら受験せずとも良かろう。」となります。
そうなると「選択問題」などの部分的な出題や重箱の隅をつつくような問題より、「大意要約」や本文に基づいた「論文形式」の方がより入試問題としては適しているし、原作者の意図との齟齬もなくなるのでしょうが、ここには一つ、採点者の労力が大変という極めて現実的な問題があるわけです。
国語を教える立場からすると、自由な解釈の下の創造的な読解と、出題者の意図を忖度するようなびくびくした読解という、矛盾した指導を取らなければいけないジレンマがあるのです。
これが日本の国語教育のダブルスタンダードです。
旧制高校の定期試験問題の鬱勃たるパトス
最後に思い出したのが、「偉大なる暗闇」と呼ばれた旧制第一高等学校の伝説的な教授、岩元禎の逸話。
彼は夏目漱石の『三四郎』に出てくる「広田先生」のモデルの一人とも言われています。
ドイツ語と哲学の一高の名物教授で、数々の秀才ですらその試験問題の難解さに歯が立たず、落第者は数知れません。中学を四年で修了した飛び級の天下の俊英たちも留年を余儀なくされました。
「彼は彼女が好きになった」という訳では許されず、自分が教えた訳「彼はかの娘に懸想したことじゃった」のようなものしか認めなかったという厳格さで、軒並みバツを食らうことで有名だったそうです。ある意味、世の中には不合理があるという教育効果をエリート達に植え付けて、謙虚さを身につけさせたという功績は大きいとも言えます。
「一生うらんでやるー!」と嘆いた一高生もさぞ多かったでしょう。今では明治時代の笑い話の一つとなっています。
お問い合わせ
お電話
0587‐74‐78990587‐74‐7899
メール
info@kyoyodo.com